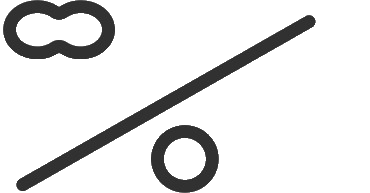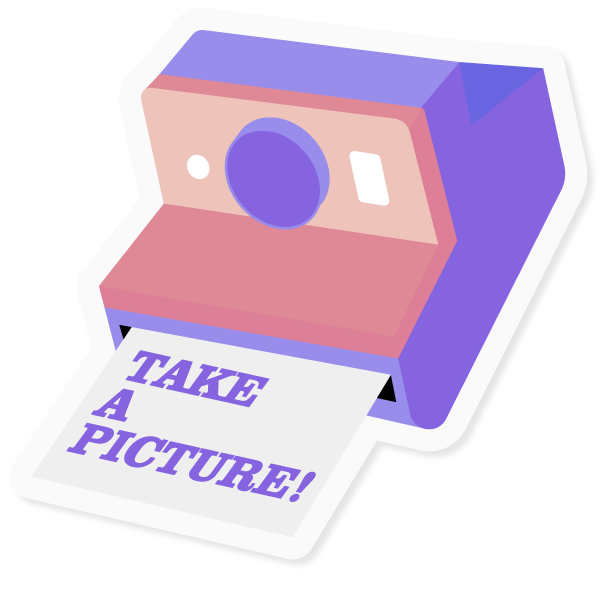シスターフッドってなんだ?
女子大学のリアルと
「シスターフッド」
「女の友情は脆い」なんて、そんなわけないけれど。男性の友情がかねてより強く尊いものとして扱われてきたのに対して、「女性の人間関係」についてはネガティブに語られてきた面があります。
そして、シスターフッドの認知拡大とともにネガティブイメージは払拭されつつあるものの、入ってみるまで実情がわからないのが「女子大学」という場所。女子大学って実際どんなところ? そもそもどうして女子だけの学びの場があるの?
「女子大学」という場で教えている/学んでいるふたりの女性にお話をうかがいました。
シスターフッド(Sisterhood)という言葉が近年、注目を集めています。
直訳すれば「姉妹関係」という意味ですが、「強く結ばれた女性同士の連帯」を指す言葉として、「#MeToo運動」の盛り上がりなど、フェミニズムの認知拡大が世界的に高まるとともに、シスターフッドというキーワードも認知されてきています。また、シスターフッドをテーマにした文学・映画・ファッションプロダクトなどが次々と生まれています。
「女子校ってネチネチしてそう」
そのホントのところは?
今日はよろしくお願いします。まずは簡単に、先生の専門分野を教えてください。

人権教育の理論構築を研究テーマとし、日本に住む外国ルーツの人々の支援など社会活動に関わっている。甲南女子大学の女性教育の今後を考えるプロジェクト共同者。ご自身は生粋の女子校育ち。
野崎先生:私は教育社会学、人権教育……とくに多文化共生のための教育について研究しています。ゼミでは、日本のエスニックマイノリティをめぐる多文化共生の課題をテーマにしています。長田区にある「神戸定住外国人センター」で、学生が外国にルーツを持つ子どもたちに勉強を教えたり交流するなかで、社会が抱えている問題について理解しながら解決の糸口を探す行動演習という授業があります。

野崎先生のゼミ生で、外国にルーツを持つ子どもの学習支援活動にも参加。韓国カルチャーに興味があり、自身も韓国に留学経験を持つ。現在は就職活動に邁進中。共学校出身。
※現 国際学部 多文化コミュニケーション学科
窪田さんは先生のゼミ生なんですね。
窪田さん:はい。1年の時の担任的な立場の先生だったのが野崎先生で、2年に上がるのと同時にさまざまな先生が開講しているゼミに選択して入るんですが、私はそのゼミも野崎先生だったので、4年間、野崎先生に教わっているかたちになります。
近年、シスターフッドと呼ばれる「女性同士の繋がり・友情」をテーマにした作品が多く発表されて支持を集めています。女子大学はまさにシスターフッドの場と言えるかもしれません。おふたりの経験をベースに、シスターフッドについてお話いただけたらと思います。先生と窪田さんはそれぞれ学生時代は共学出身でしたか?
窪田さん:そうですね。私は高校までが共学校でした。甲南女子大学に進学して、はじめて女子学生だけしかいない場所で過ごしています。
野崎先生:私は出身が女子校でかつエスカレーターだったので、小中高大と、ずっと女子校でした! 大学院ではじめて共学になったんですが、それまではもうずっと女子校育ちです。
おおすごい! それぞれ共学・女子校出身だからこそお聞きしたいんですが、女子大ってどうですか?

窪田さん:私は第1志望は共学の私大で、女子大であることを志望していたわけではないんです。もともと韓国のカルチャーに興味があって、甲南女子の「多文化コミュニケーション学科」では留学もできると知って、ここに進学しました。共学から女子大に進学した身としては……楽ですね!
女子大って「人間関係がネチネチしてそう」といったネガティブイメージがあると言われますが、実情はそんなことないですか?
窪田さん:ないですね……。私自身も、入学するまではドロドロしてるのかな? とか考えて、女子大って人間関係が難しそうだと思っていたんですが、実際はそんなことなかったです。同性ばかりなので安心感があります。友達も自分の学びたい分野をそれぞれ学んでいるからここに来ているという感じで、いつもべったり一緒というわけではないですし、タイプの違う友達と一緒になることもたくさんあります。
窪田さんの周りには、たとえばどんな人がいますか?
窪田さん:誰にでも明るく声をかけてくれる人が多いように思います。私自身はどちらかというと控えめな性格で、自ら声をかけたりすることが苦手なのでありがたいです。自分と同じ趣味を持っている人もいますし、すごく勉強熱心で毎日研究に励んでいる人、課題について相談できる人など、性格もさまざまな友達がいます。
先生もなにか女子校がゆえの楽しいエピソードってありますか?
野崎先生:いかに身を削って笑いを取りにいくか、面白いことをするかということに必死になったりして。ついエスカレートしてしまって、みんなでお腹が痛くなるほど笑っていました(笑)。個性的な同級生が本当に多かったです。しかも、そういう個性は、イジられつつもちゃんと認められてました。もちろん、当時は共学への憧れもありましたけど、振り返ってみると、お互いの良い面も悪い面もひっくるめて、ありのままをさらけ出せる関係を築いてきたから、卒業後もずっと仲のいい友達と交友が続いていますね。
私の周りにも女子校出身者って結構いるんですが、おふたりのように「楽しかった!」という意見がほとんどですね。
女性同士の関係性に対する
イメージや偏見は、
男性社会が長く優位だったから

しかし「女性同士の人間関係」と聞くと、あまりピンとこない人もいたり、女性の友情なんてないでしょ! という人もいたりするんですよね。ネットで「女性の友情はハムより薄い」なんて書かれているのも見てしまって……。どうしてそういうイメージがついてしまっているんでしょう?
野崎先生:推測ですけど、長い歴史のなかで、男の人のストーリーというものがメインであることが多かったからじゃないでしょうか。
それってどういうことですか?
野崎先生:人間と人間の社会を描くときに、どうしても男性がそのストーリーの主体になってきましたよね。歴史は「権力者の歴史」として描かれる傾向がありますから、日本史でいえば、繰り広げられてきた戦乱や動乱の歴史はまさに男と男の物語じゃないですか。
確かに!
野崎先生:「意味のあるコミュニティ」として描かれてきたのは圧倒的に男性のコミュニティが多かったのかもしれません。私の専門ではありませんが、スポ根マンガなんかも、『アタックナンバー1』などが発行される1970年代までは男性のものだったのではないでしょうか。一方、女性のコミュニティはそもそもあまり描かれなかった。描かれても、かなり限定的だったのではないでしょうか。
女性同士のコミュニティが創作の場で描かれても、すぐに「恋愛バトル」的なストーリーになってしまうことが多かったように感じます。
野崎先生:女性は、権力のある男性と結ばれることでしか自分の主張ができない時代もありました。だから、女性個人が描かれる場合も、すぐに婚姻や恋愛に絡められることが多いのかもしれませんね。
女性に友情はないかと言われると、決してそんなことはないんですよね。いつの時代にだって友情が芽生えるのは男女同じはずなのに。近年になって「シスターフッド」と呼ばれてそれが可視化されてきたのは、女性のコミュニティが捨象される時代が終わったことを表しているのかもしれませんね。
野崎先生:女性同士がしっかり繋がって支え合える関係性を築くことは、今なお必要なことなんじゃないかと思います。ちょっと堅い話になりますけど、歴史的にも、女性は連帯することによってようやく男性と同じ権利を獲得していくことができました。1970年代頃には、日常の女性の生きづらさの経験が、単なる「個人の問題」ではなく「社会の問題」だと認識され、社会に埋め込まれた性差別を明らかにしてきました。その時も、女性同士が自分たちの経験を共有しあったり、連帯することが、とても重要な意味を持っていたと思います。
そうした連携による権利の獲得で、今日があるんですね。
野崎先生:そうですね。それから随分変化もありますが、残念ながら今も女性にとって困難な状況はありますよね。そして、その困難の多くは大学を卒業して社会に出てから直面することが多い。だから、そうなった時に孤立せずにしっかりと繋がって支え合える、女性同士の絆を大学時代に築いておくことは一層重要なんです。
女性だけだと
個々人の多様性が見えやすい

女子しかいないなかで、共学の時と比べて女友達の見え方が変わったということはありますか?
窪田さん:共学の時は、仲の良い友達は固定されていたように思います。というのも、小中高ってほとんどの場合、だいたい男女半々のクラスに分けられるじゃないですか。選択授業などがない限りは1年間同じメンバーと学校生活を送ることになりますよね。
そうですね。
窪田さん:そうなると、まず自然と男女で分かれて、そこから仲良くできる子を探す感じになるんですよね。女子学生のなかでもグループがあり、男子学生の中にもグループがあって、そのグループの垣根を超えることは、体育祭や文化祭などのイベント以外にはあまりなかったように思います。「固定」と言っていいほど、共学時代は、仲の良い友達は限られていました。
わたしも共学校だったのですごくわかります!
窪田さん:女子大学に入ってから感じたことは、みんな良い意味で「浮遊」している、ということです。というのも、大まかなグループは存在しているものの、授業ごとにメンバーが変わるのでそのたびに話す相手が変わるんです。今までは話すことがなかったような人とも、話してみると共通点が多かったり、同じ趣味の話で盛り上がったり……。共学の時は、クラスのグループになれそうな子と仲良くなろうと必死だったのですが、女子しかいない環境では女友達というか、相手をひとりの「人」としてしっかり見ることができるようになったと思います。
お〜、なるほど。共学から女子校へ行ったからこその体験談ですね。でもどうして、女子大学……もとい女性だけの場だと相手をひとりの人として見られるようになるんでしょう。

野崎先生:男女共学のコミュニティの中で生まれるシスターフッドとは違って、女の人だけだと女性個々人が持つ多様性が見えやすいんじゃないかなと思いますね。
女性個々人が持つ多様性……。
野崎先生:男女混じり合ったコミュニティの中での個性って、「女のなかでは」「男のなかでは」と性別でそもそも大別されたうえでようやく個性が認識されると思うんです。
わ〜〜〜! わかります!! しかも「よく食べる」とか「声がでかい」とかだと、「女のくせに」というネガティブな枕詞がつきがちなんですよね……。
野崎先生:女子学生のなかに、自信がなかったり、前にでることをためらったり、失敗を恐れてチャレンジできなかったりする学生が多いのも、それまでの学校生活の中で無意識に身につけてしまった、「女性であるという制約」を自分自身に課している部分もあるからなのかな? と思うこともあります。
なるほど……。
野崎先生:女性同士だと性差で分けられないから学生個々の個性をそのまま受け入れることができる。女性にもいろんな人がいるなというのを身をもって体験できて、かつ、多様性を貫く「わたしたち」という同胞意識というか、連帯感も生まれやすいんじゃないでしょうか。もちろん女性同士だからといって一枚岩でないんですけど、社会に出た後の女性同士の足の引っ張り合いにならないための女性同士の絆と、女子大学の学びを伝えていきたいですね。
「格差のある社会で
生きぬくための力を」
令和における女子大学の意義

同性同士しかいない空間だからこそ得られるコミュニティ意識や個性の認識など、女子大学が女性たちにもたらすものの価値はわかりました。ただ一方で、「男女関係なく進路を自由に選べる時代になったから、女子大の役割は終わった」という意見もありますが、いかがでしょうか?
野崎先生:大学設立の時代と比べたら、比較にならないほど女性の教育における状況は改善してきました。でも、まだまだ気にせざるを得ない世の中がありますよね。
そうですね。確かに、医学部入試の女性差別問題や東大合格者における女子の割合の低さなど、格差が解消されたとは言えません。それに日常の小さな瞬間にも「女性であること」を強いられる瞬間ってまだまだありますね。窪田さんもそう感じる瞬間っていままでありましたか?

窪田さん:私自身、「女性であること」を強いられた経験はないように思います。学校は守られている環境だと感じるからですね。ただ、これから社会に出ていくにあたって、女性であるためにチャンスが減ったりだとか、不平等がもしかしたら待ち受けているかもしれないと思うと、漠然とした不安や怖さはあります。
野崎先生:かつては大学から排除されてきた女性が、戦後になって男性とともに大学に入れる時代になっても、まだまだ当時は男性ばかりの大学には行きづらかった。そういう背景もあって、女子大学ができました。男性とのギャップを埋めるために設立された女子大学ですが、だいぶん解消されてきたとはいえ、世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で日本のランクは120位と先進国の中でも最低ランクです。格差を多くの女性が経験する世の中である以上、女子大学の役割は終わっていないと思っています。
収入平均値も男女でかなり差がありますもんね。結婚して名字を変えるのがほぼ女性側だというのも格差のひとつかもしれない。
野崎先生:性別による役割分業意識が格差の原因になっているんですね。格差をもたらしている社会があって、その社会によって女性が生きにくさを感じている以上は、女性を力づけていく教育機関は“残念ながら”まだまだ存在意義があると思っています。
男女差別がなくならない限り、女子大学も必要ということですね。
野崎先生:本当はいちいち「女性は…」「男性は…」と言う必要さえなくなるのがいいんですけどね……。そういうカテゴリー自体は、これからもなんらかの形で機能し続けるでしょう。でも、女子大学の存在意義は未来永劫ではない。というか、未来永劫あってはいけないと私は感じます。
女性だけしかいない環境の
居心地のよさに
甘んじない教育が必要

男女の格差を解消していくための女子大学ですが、「どんな教育をするのか」も非常に大事な気がしました。
野崎先生:そこなんですよね。どんな教育をするのかが女子大学は非常に重要です。学問に向き合うときも、女性学の視点でものを考えてみるとか。社会に出た時に、世の中が……あるいは自分自身が「女性」であることで自分自身に縛りをかけていることに気づいたり、きちんと声をあげられるのか。どうせ自分は……と自分自身の可能性を狭めてしまっていないか。社会に出るまでの4年間のあいだに下積みを重ねて、備えてほしいです。もちろん、自分自身が誰かに同じような縛りをかけていないか、ということに気づくためにも。
女性だけしかいない環境の楽さに甘んじてはいけないということですね。
野崎先生:そうなんです。「女子しかいないから楽」というのはプラスではあるんですが、これって非常に特殊な環境なんですよね。一般社会とは明らかに異なる。特殊な環境下による楽さであることは肝に銘じておかなければいけないんです。教える側も教わる側も。特殊な環境下で何をするのかが明確にされていなければ、ただの温室になってしまいます。
卒業して一歩出れば男性がたくさんいる世の中を歩いていかないといけないんですもんね。
野崎先生:もちろん、在学中に男性と触れ合う機会がゼロというわけではないですけどね。学内に男性の教職員もいますし、アルバイト先で男性社員や男子学生に会う機会は多いですし。
たしかに、そうですね。
野崎先生:大学の中ならバリバリ活躍できるのに、男性が混じると途端に本領を発揮できない学生……とかね。やっぱりいるんです。女子大学という特殊な環境は、自分の過ごし方次第で弱点にもなりうるということを自覚したうえで、その特殊な環境を大いに利用して、貪欲にチャレンジしてほしいです。そして、その特殊な環境だからこそできる学び、受け取ることのできる力とメッセージがある。社会に出ても、お互いに支え合えるような絆を育んでほしい。私たちはそのサポートをしっかり担っていかなければいけない。女子大学はきっと、その存在意義をずっと試されているんです。
「女性の自立のバトンをつなげ続ける」
というシスターフッド

「シスターフッド」をテーマに今回お話をおうかがいしたんですが、「女性だけ」の場であることのメリットや魅力だけではなく、性差のなかで女性たちがどう生きていくのか、そのサポートの場であるという女子大学の意義と課題も知ることができて非常に勉強になりました。
野崎先生:ある研究によると、女子大学で勤務する教員は共学で勤務する教員よりも、(男性教員も女性教員も)女性の社会的課題により関心を払う傾向があるそうです。実際に、本学でも女性の問題に関心を持っている男性の教員は少なくないです。一方女性の教員は、やはり同じ女性という記号を持っている同志というか、若い世代の学生たちに、こう……「なんとか生き抜いてくれよ!」という、少し特別な気持ちがあるかもしれません。そういう考えを持った女性の先生って実は多いんです。次の世代へのバトンをどんなふうに渡せるのかをすごく考えている。そう考えると、女性教員と女子学生との間にも、シスターフッドがあるのかもしれません。
バトンをつなげるということがシスターフッド……。
野崎先生:期待が高いがゆえに厳しいことも言ってしまうんですけど(苦笑)、同じ女性として豊かな人生を送ってほしいですし。辞めていかれた女性の先生もみんな、女子学生のことを気にかけていらっしゃいます。女性たちが繋げてきたバトンを私も次に渡さなければいけませんし、窪田さんを含めた若い世代も、このバトンをさらに下の世代へと繋げてほしいなと思いますね。

国際学部 多文化コミュニケーション学科についてはこちら(大学公式サイトへ)
野崎志帆教授の教員詳細ページはこちら(大学公式サイトへ)
※記事に記されている所属・役職等は取材時のものです。既に転出・退職している教員、卒業している学生が掲載されている場合があります。

[シーソー]って?



遊びが学びに、学びが遊びに。
いま、あなたの目に映る何か。
あなたの心をどうしようもなく惹きつけている何か。
角度を変えれば、遊びが新しい学びに、学びがとびきりの遊びになる。
私の近くの、私の中の、日常の些細なことが、未来を作る。
[シーソー]は、そのことに気づくきっかけになりたい。
キャンパスマガジン[シーソー]、はじまります。